「家、ついて行ってイイですか?」から学ぶ企画論
最近攻めてるテレビ局
普段は全然テレビは見ないのですが、それでもついついみてしまうのがNHKとテレビ東京。
全然真逆ですけど、最近のNHKは社会現象にもなっている「チコちゃんに叱られる!」を始め、バラエティがめちゃ面白い。
最近、ネットニュースでも盛んに取り上げられていますね。
なんでも、元フジテレビで「笑う犬」を手がけていたプロデューサーの方が関わっているとのこと。
最近のNHKは、お堅いイメージのNHKをぶっ壊すチャレンジを続けているので目が離せなくなっています。
そしてもう1つがテレビ東京。
他の在京キー局と違い、独自路線を突っ走っていることで有名です。(何か大きなできごとがあっても通常放送を続けるのが一種のテレ東式のようなイメージですね。笑)
そんなテレ東の番組の中で異彩を放っているのが、家、ついて行ってイイですか?という、街で突然声をかけた人の家についていき、その人の人生模様を聞いてそのまま放送するドキュメンタリー番組。
5月に起こった池袋の高齢者ドライバー事故では、事故が起こる前日に、以前交通事故で家族を亡くした方への取材をしていたものが後日放送され、その偶然性が話題となりました。
この番組をつくったテレ東ディレクターの高橋弘樹さん。
今回は、斬新な企画を連発する高橋さんの企画論について一緒に学んでみましょう(^^)
ヒットメーカーの企画術
彼が企画を考えるときに意識していることをひと言でまとめると、ジャンルの常識を根底から覆す。ということです。
これは言わば、皆があたり前と思っている「あたり前」の概念に対して挑戦状をたたきつけるということです。
高橋さんは、この「常識を覆す」ことが資金力が無く認知度も低いテレ東流の弱者の戦略だと言います。
たとえば、「家、ついて行ってイイですか?」は番組のジャンルで言うとドキュメンタリーに分類されます。
それまでのドキュメンタリーの常識は長期間取材が前提でした。
たしかに、僕たちの中でもドキュメンタリーは2年、3年にわたって密着取材し最終的に映像にまとめたものというイメージがあります。
でも、「家、ついて行ってイイですか?」ではディレクターが「タクシー代をお支払しますので」とその場でアポをとって一緒にその人の家にいきます。
この、長期密着ではなく短期決戦の意外性こそ、ドキュメンタリーの分野でのジャンルの常識を根底から覆すということになり、結果として番組がヒットする要因となりました。
そのままの「生」を見る
そして短期決戦はもう一つの意外性を生みます。
通常、一般の人の家に取材にいくとなると、事前にアポイントをとりますよね。
ニュースでも、一般の方のお宅に伺う時にピンポーンと玄関のチャイムを鳴らし、初めまして〜という場面からスタートします。
でもこの場面、何か違和感を感じませんか?
そう、応対する奥さまが「メイクとヘアセットバッチリ!」「部屋の中もめっちゃキレイ!!」
突然訪問した感を演出していますが、人間の心理としてテレビに出るとなると少しでも良く写りたいという心理が働きます。
「家、ついて行ってイイですか?」ではアポをとってそのまま訪問するので片付けをする時間が無い!ということは、その人のそのままの「生」が映し出されるわけです。
これが、これまでのドキュメンタリーに無かった意外性その2。
そしてその番組を支えるのが70名ものディレクターとテーマソングのLet it Be.
通常TV番組は多くて4,5名。24時間テレビでも30名くらいとのこと。
でも、この番組は70名ものディレクターが日々街に出て、声をかけ続けているとのこと。
この量の差が、映像の質を決めるんです。
そして「家、ついて行ってイイですか?」ではテーマソングのLet it Be以外、ナレーションや音楽はありません。
これもこれまでのドキュメンタリーではあり得なかったこと。
高橋さんは、ナレーションや音楽を加えると、作り手が視聴者の感情操作をしやすくなる。でも、「家、ついて行ってイイですか?」では、視聴者ごとに受け取り方を変えて欲しいので、敢えてナレーションや音楽を入れていないと言います。
これも、ジャンルの常識を根底から覆すの1つですね。
斬新なアイデアは「当たり前を理解すること」から始まる
このような斬新なアイデアを生み出すために必要なことを高橋さんはあたり前だ、と思われているルール基本構造を理解すること、と言います。
つまり、まずはこれまでの常識を徹底的に理解することが最初で、それがあって初めて、従来との違いをどのように出していくか、を考えることができるようになるということです。
これは別にテレビの企画だけでなく、どの業界においても通じることです。
例えば阪井の場合も、ブログ集客のセミナーをやっていましたが、その時のテーマが毎日ブログを書かなくて良い!アクセスに頼らないブログ集客術でした。
このセミナーの結論は、薄い関係性ではなく濃い関係性をつくろうという、阪井がいつも言っていることなのですがブログ集客においては
- アクセス数が大事
- とにかくブログは毎日書くことが大事
という共通の理解があったのでそれを踏まえた上で、それとは180度逆のジャンルの常識を根底から覆すを行ったところ大ヒットしました。
このように、まず常識を理解し、そこから180度逆のことをコンセプト化(もちろん、それをきちんといえるだけの実績は必須)ということをすると、それを見た人は頭の中に自分の常識で理解できない???が浮かぶので興味を持ってもらうことができる、というわけです。
まとめ
今回は、TV番組のディレクターから学ぶ企画術というテーマでお届けしました。参考になれば嬉しいです(^^)
今回の内容については、高橋さんの著書から引用させていただきました。
非常に面白いのでぜひ読んでみてください(^^)
1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術
ちなみに、こういった他分野と共通していることを抽象化して自分の分野に適用させる思考のことをアナロジー思考と言います。
ということで、今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
(株)CarpeDiem代表取締役
ValuenceAcademy(バリューエンス・アカデミー)主宰
起業エンジンメーカー
『明日目覚めるのがワクワクする社会の創造』をテーマに<人の可能性を最大化する>事業を展開。
相手の笑顔のシワの1つ1つまで見えるような「距離の近い」事業づくりが目標。
珈琲/イチゴ/エビ好きな旅宿マニア
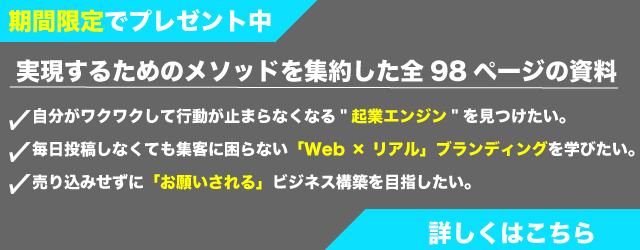

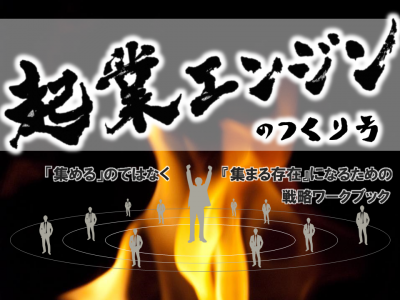

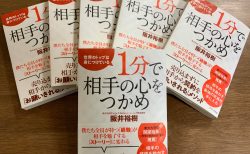

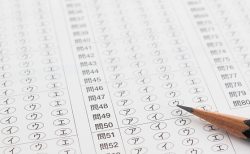




facebookでコメントする。