主体的に動けるようになるための脳科学の話
人間は反射で生きている
世界的名著の「7つの習慣」にも書かれていることですが、人間は基本的に反射で生きているため、物事に対して理屈や考えをあまり必要としない生活をしています。
つまり、思考する、もっと言うと、考えて動く、前回のブログでも書いた「知覚動考」を普段からあまり行っていないため、「自分で考えて動く」ということが非常に苦手です。
でも、起業して結果を出すには、自分で考えて動くこと、主体的に動くことが必須条件です。
今回はそんな、反射的な生き方から主体的な生き方に変化させるには?ということを、脳科学の観点から掘り下げていきたいと思います。
人間の脳にある2つのシステム
ノーベル経済学賞を受賞した認知心理学者のダニエル・カーネルマン博士は著書「ファスト&スロー」で人間の脳には「システム1」と「システム2」という2つのシステムが存在すると解説しています。
システム1は自動的に高速で働き、努力が要らないシステム。
自分のほうからコントロールしている感覚は一切無いシステムです。
たとえば、私たちは1 + 1 = ??という数式を見た時に瞬時に答えを出すことが出来ます。
このように、考えずに反射的な行動をする脳の働きを、カーネルマン博士はシステム1と読んでいます。
一方、システム2は遅い思考。
複雑な計算など頭を使わなければ出来ない知的活動にしかるべき注意を割り当てる思考のことです。
たとえば、79 ×82 = ??のような計算式が出た際に私たちは直ぐには回答できず、意識的に脳を使い「考え」はじめます。
システム1の反射を超えて、意図的に考える。
これがシステム2が稼働している状態であり、主体的に生きているという状態です。
システム2はタスク設定が出来る
カーネルマン博士曰く、主体的に動くシステム2を発動するためのポイントは、タスク化できるかどうかとのことです。
システム1の反射レベルだと自分で考えるということを行わないため、そもそも意図的に判断することが出来ない。
一方、システム2が起動している状態だと反射ではなく自分で考えるという段階にいるため、脳を使いタスク設定が出来る。
そのため、反射的な生き方から主体的に行動できるようになるための1つの基準は、その行動が「タスク化できるかどうか」で判断することが出来ます。
疲れたら甘い物が欲しくなる理由
とはいえ、ずっと考えてばかりいると疲れてきます。
私たちは疲れると甘いものが欲しくなりますが、実はこの反応はシステム1の影響によるものです。
カーネルマン博士によると、反射的なシステム1は実は大の甘党とのこと。
つまり、何か物事を考えているときに甘いものが欲しくなったら、それはシステム2のシステム1への監視が効いていない状態です。
システム2は反射的な反応を抑えるいわば監視役の役割も持っていますが、システム1をずっと監視することは出来ません。
システム1が優勢になってくると、甘いものが欲しくなり、ギブアップしたいという欲求に駆られます。
そんな時は正しい思考が出来なくなっているので一度頭を休めてください。
システム2を優勢に保つには
主体的に動くためには、インセンティブ(ご褒美)が効果的です。
システム1は甘党のため、ついつい目の前の利益(甘いもの)にとらわれてしまいますが、それ以上のご褒美が後で待っているとシステム2が働き、目の前の誘惑から逃れることが出来ます。
反射的な行き方から主体的な生き方になるには、実はこのようなご褒美作戦も効果的なんですね。
起業して結果を出すには
起業して結果を出すということは本当に毎日コツコツやることでしか生まれません。
システム1に支配され、反射的な気分でやったりやらなかったりではいつまで経っても結果には繋がりません。
今回私が伝えたいことは、脳のシステムについて理解し、上手く付き合っていくということの必要性です。
理解していないと、「どうしてできないんだろう」と落ち込んでしまいますが、きちんと脳のシステムを理解しておけば、対策を打つことが出来ます。
こういったヒントを元にして、ぜひあなた自身が「主体的に動く」設計を行ってください。
主体的に動くには
バリューエンス・アカデミーでは、「行動が変わる」ためのメールマガジンを無料で火・木・金の週3回配信しています。
ブログ記事をお読み頂いて、更に学ばれたい方は、下記のリンクよりご登録ください。
(株)CarpeDiem代表取締役
ValuenceAcademy(バリューエンス・アカデミー)主宰
起業エンジンメーカー
『明日目覚めるのがワクワクする社会の創造』をテーマに<人の可能性を最大化する>事業を展開。
相手の笑顔のシワの1つ1つまで見えるような「距離の近い」事業づくりが目標。
珈琲/イチゴ/エビ好きな旅宿マニア






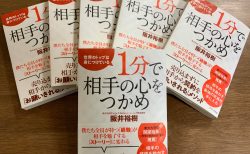

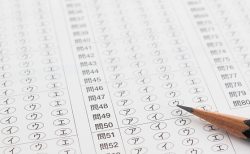




facebookでコメントする。